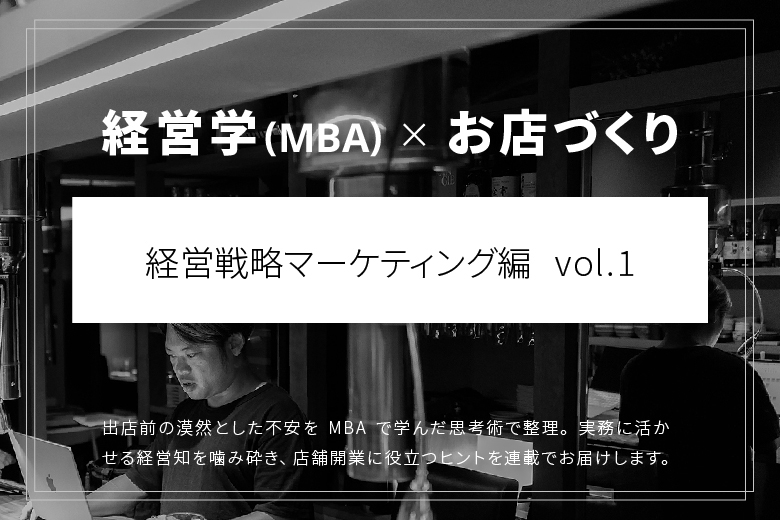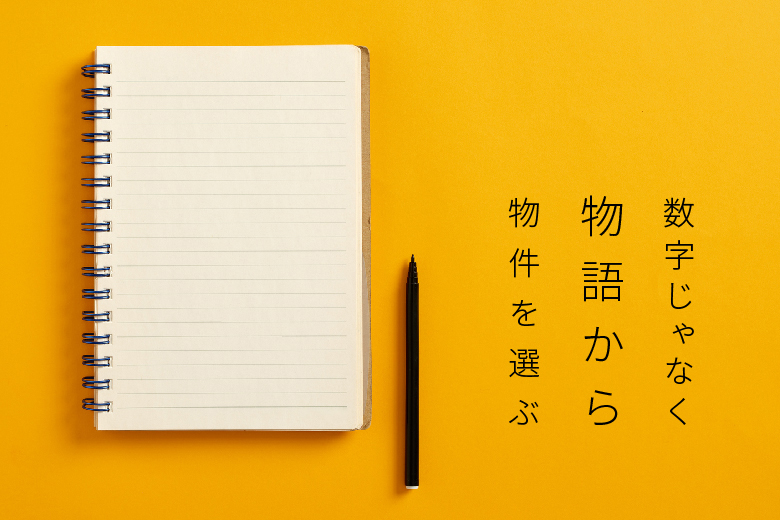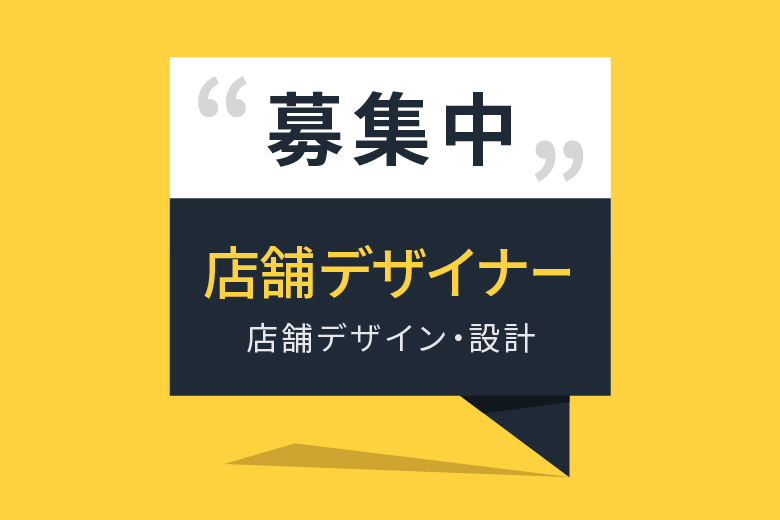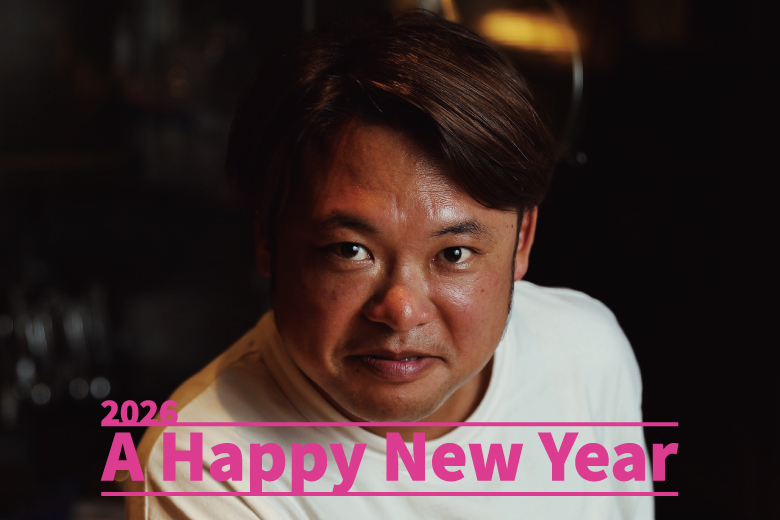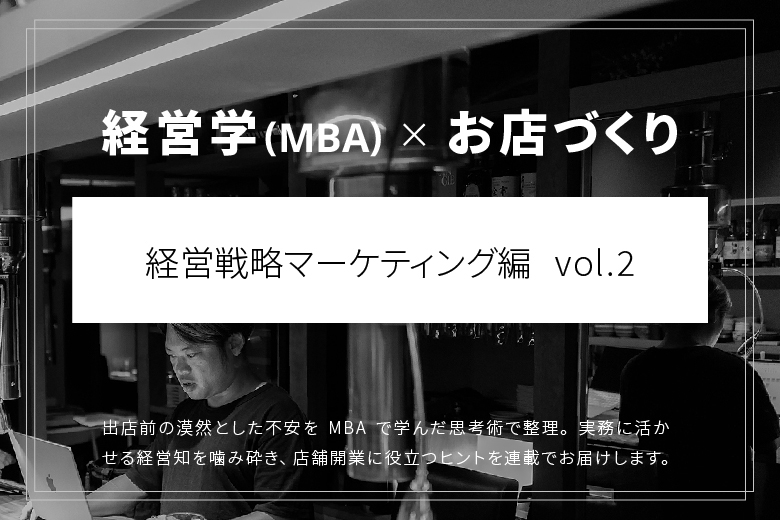
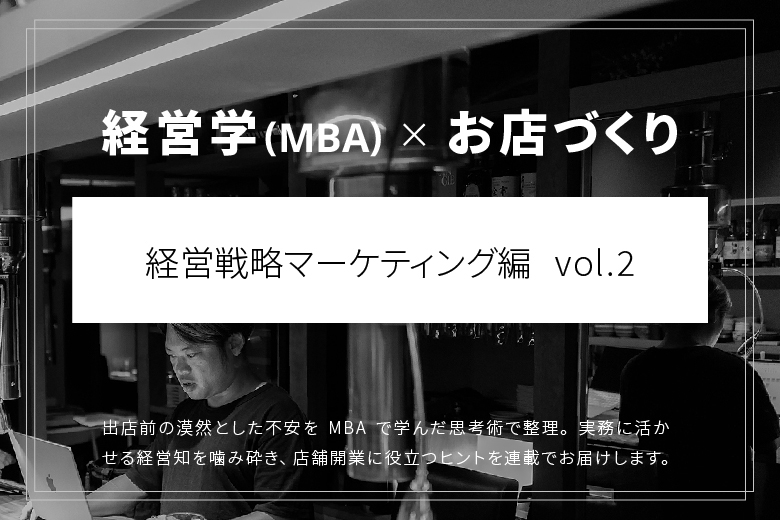
価格では勝てない時代に、お店が選ばれ続けるには?模倣困難な価値の築き方を、MBAでの学びから考える。
忙しい日々でも、学びを止めない理由
今年からグロービス経営大学院(MBA)での学びをお店づくりに活かしたいとはじめた連載も第五弾。今回は「競争優位」がテーマです。実はこの春から、新しい事業を立ち上げる動きも進めていて、「始動 Next Innovator」というプログラムにも採択されました(全国から100名が選抜)。これも、MBAでの学びの中から自然に芽生えたアイデアです。
そんなわけで、最近はコトスタイルの業務をしながら、週末は東京で講義、平日は夜にプログラムと、なかなかバタバタ。でも不思議と気持ちは前向きで、むしろ言葉にしておきたいことがたくさん出てきています。
このブログシリーズも、その一環。第5弾となる今回は「競争優位性」について、学びと実務をつなぐような形でまとめてみたいと思います。
「差別化」だけじゃ足りない? 持続的な優位性とは
マーケティングでよく出てくる言葉に「KSF(Key Success Factor)」があります。要するに、その業界・市場で成功するための鍵になる要素。でも、KSFを見つけて、そこに集中するだけでは「競争優位」とは言えない。
なぜなら、それは他社も同じように見つけて、同じように実行する可能性が高いからです。いわば「一時的な差別化」にすぎない。
今回の講義で何度も出てきたのが、「持続可能な競争優位性(Sustainable Competitive Advantage)」という言葉。これは「真似されない・代替されない・長期的に有効な価値をどう築くか?」という問いにほかなりません。
「うちのほうが安くていい」は、すぐに真似される
特に個人店や小規模事業者にとって、「いいものを安く提供する」戦略は、わかりやすいし、ついやってしまいがち。でもこれは、実は最も競争優位を築きにくい方法です。なぜなら、価格は簡単に真似されるから。
例えば、仕入れルートが違うから安く出せる──それも一時的には有効かもしれません。でも、すぐに他社が追随する。結果、疲弊戦になる。
だからこそ「模倣困難性」が大事なんです。
たとえば、こんな店舗は強いですよね。
-
自社農園で育てた野菜しか使わないレストラン
-
店主が毎朝市場で買い付ける魚しか出さない寿司店
-
地域内で複数店舗をドミナント展開しているカフェチェーン
これらに共通するのは、「他者がすぐに真似できない運営の仕組み」があること。価格や味、接客だけじゃない、「設計された仕組み」こそが競争優位を支えているんです。
バリューチェーンで考える、あなたのお店の“武器”
今回の学びで印象的だったのが「バリューチェーン」の視点です。
商品やサービスが「原材料の仕入れ → 製造 → 流通 → 販売 → アフターサポート」と流れていく中で、自分たちのビジネスがどこに強みを持っているのかを分解して考える。
これは、飲食店でも物販でも、同じように応用できます。
たとえば、コトスタイルのビジネスで考えてみましょう。
-
テナント物件の選定(不動産仲介)
-
内装設計(店舗デザイン)
-
施工(工事・現場管理)
-
開業支援(販促・補助金・MEOなど)
この一連のプロセスをすべて自社でサポートしている点が、他社との大きな違いです。
多くの会社が「物件仲介だけ」「デザインだけ」「工事だけ」と分業化されている中で、コトスタイルは“お客様の開業”という目的から逆算して、一貫した流れをつくっている。これが、簡単には真似されない「価値の連なり=バリューチェーン」だと再確認できました。
「競争優位」は、旗ではなく積み上げる土台
では、実際に自分たちのビジネスにおいて、競争優位はどう築かれるのか。
それは「うちのウリは〇〇です」と掲げるものではなく、日々の積み重ねのなかで自然と形づくられていくものなんだと思います。
日本政策金融公庫の事業計画書でも、競合との違いや模倣困難性を書く項目がありますよね。でも実際には、「安く仕入れて高く売る」なんて単純な話じゃない。
お店の雰囲気、スタッフの対応、商品開発の背景、SNSの活用、地域との関係性──すべてが複雑に絡み合って「このお店、なんかいいよね」という感覚につながっていく。だからこそ、「どこが強みか?」を改めて構造的に見直すことが大切。
特にお店の立ち上げ時こそ、こうした「競争優位」をどうつくるかをしっかり考えるチャンスです。とはいえ、実際にはそれをずっと考え続けていくのが経営なんですけどね。
まとめ:選ばれるお店には、ちゃんと理由がある
今回のMBA講義で改めて感じたのは、「選ばれる理由」をつくる難しさとおもしろさ。
価格や立地だけじゃなく、競合にはない“何か”を持っている店が、やっぱり強い。その“何か”は、現場のオペレーション、バリューチェーン、提供価値、ブランドストーリー、どこからでも生まれうる。
「このお店でないといけない」と思ってもらえる理由──
それこそが、競争優位であり、経営の本質だと思います。
忙しさに追われる日々でも、少し立ち止まって、「自分たちにしかできないことは何か?」を問い続ける。
そんな時間を、これからも大切にしていきたいです。